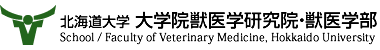市民公開講座「我が国のBSE発生から20年が経過して -混乱から生じて現在に引き継がれる社会変容-」のお知らせ
主催: 北海道大学One Healthリサーチセンター
共催: 厚生労働科学研究費「食用動物等のプリオン病の病態機序およびヒトへの感染リスクの解明に関する研究」、
APPS (Asian Pacific Prion Symposium) 2024、北海道大学One Healthフロンティア卓越大学院プログラム
日時: 2024年11月30日(土)11:00~12:30
場所: 北海道大学獣医学部 講堂(札幌市北区北18条西9丁目)
参加費: 無料
申込方法: 申し込み不要
問い合わせ先: 北海道大学大学院獣医学研究院・獣医衛生学教室
メール:
2001年に我が国でBSEの発生が確認されてから20年以上が経過しました。サーベイランス、飼料規制、トレーサビリティーの導入により、当時世界的に問題となっていた定型BSE(C-BSE)の発生は世界的に制御下にあります。ただ、2024年に英国でC-BSEが摘発されたように、根絶されたわけではありません。
BSEは伝播力が弱いウシの病気です。しかし、ウイルスや細菌と異なり、遺伝情報の担い手である核酸を持たず、タンパク質から構成され、各種消毒・滅菌法に著しい抵抗性を持つ「プリオン」と呼ばれる病原体の特殊性、治療法がない致死性の病気であること、「食」という不可避の行動を介してヒトが感染する可能性があること、などから、社会が脅威と不安を感じ、世界的に大きな混乱を生じました。
困難な状況に陥るほど、人間の英知は発揮され、問題を克服するための大きな社会変容をもたらします。当時を振り返ると、1996年の腸管出血性大腸菌大規模食中毒、2000年の黄色ブドウ球菌大規模食中毒事件に続き、 2001年に我が国初となったBSE感染ウシの摘発は、食の安全・安心を根底から覆す出来ごとであり、食品安全基本法の制定、食品安全委員会の設置、科学知見に基づくリスク分析、ステークホルダーを交えてのリスクコミュニケーション、トレーサビリティーの導入など、多くの変化をもたらしました。その変化の中には、緊急時対策として、食肉衛生検査にBSEスクリーニング検査を導入して人への感染を絶つという、不可能を可能にするような、劇的な事例もありました。
この歴史的な出来事を風化させずに、将来への教訓として語り継ぐために、折に触れ振り返る必要を感じます。本市民公開講座は、BSE発生に伴い私たちが学び経験した「正の遺産」を将来の糧として、新たな感染症対策、食の安全・安心に活かすことを意識して、当時の騒動の最中で奮闘した方々から話題提供いただきます。
講演者:
- 吉川 泰弘 先生 共和化⼯・環境微⽣物学研究所東京⼤学名誉教授
「⽇本のBSE発⽣から約四半世紀を経て」
- 川越 匡洋 先生 厚⽣労働省健康・⽣活衛⽣局⾷品監視安全課
「我が国におけるBSE発⽣後の対応について−厚⽣労働省における対応−」
- 菊池 栄作 先生 北海道⼤学One Healthリサーチセンター社会連携部⾨
「⾷品安全委員会のBSEに関するリスク評価」
- 岩丸 祥史 先生 (国研)農業・⾷品産業技術総合研究機構 動物衛⽣研究部⾨
「⽜海綿状脳症(BSE) 今昔」
- 平野 誠 先生 株式会社ゼンショーホールディングス
「「BSE と⾷の安全」の取組み」
→ 詳細はこちら