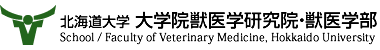- Home
- 獣医学部/獣医学研究院について
- 北大獣医の活躍
カッター先生による獣医学教育

John Clarence Cutter, B. Sci., M. D.
ジョン・クラーレンス・カッター先生はマサチューセッツ農科大学とダートマス大学医学部で学ばれた後、1877年ハーバード大学医学部を卒業、翌1878年に札幌農学校教授、開拓使顧問医として来日されました。契約期間は2年でありましたが、愛惜されて8年4ヶ月在札され、1887年に帰国されました。この間、1880年本学において初めて獣医学と水産学を講じられ、学生に最新の知識を授けられました。わが国の獣医学、水産学の濫觴です。
これらの学生の中から、池田 鷹次郎(後に南と改姓、第二代本学総長)、内村 鑑三(開拓使勤務・水産担当、キリスト教無教会主義創始者)、太田 稲造(後に新渡戸と改姓、東京帝国大学教授・国際連盟事務次長等を歴任)、広井 勇(東京帝国大学教授・土木工学専攻)、宮部 金吾(北海道帝国大学農学部教授・植物学専攻、文化勲章受章)等、有為な人材が輩出されました。
先生はこれらの専門科目のほか、英語・英文学その他の多くの科目を担当されたのみならず、校医としてまた開拓使顧問医として官立札幌病院で指導にあたられました。
人となりは精力的且つ敢為、信念に忠実で怖れることなく、真に正直で、自分にも他人にもそれを求めました。
市川厚一先生とタール癌
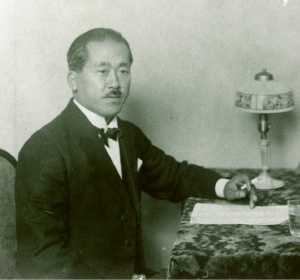

癌研究史上不滅の業績、当時ノーベル賞の候補にもなりましたあのタール癌は本学部の先輩、市川厚一博士の忍耐と努力の結晶のたまもの。茨城県出身のこの俊才は現北大・獣医学部の前身、東北帝国大学農科大学畜産学科を卒業後、大学院に進むとただちに東京帝国大学の山極勝三郎先生の下に特別研究生として師事しました。1913年のことです。彼は発癌刺激説(ドイツのウイルヒョウ博士が初めて提唱しました)を固く信じ、来る日も来る日もウサギの耳にタールを塗り続けました。実験例数101、期間70~450日、癌ができたのは31頭でした。このとき、東京大学に来てから3年の月日が経っていました。この仕事はノーベル賞候補に挙げられましたが、対立候補のデンマークのフィビガー教授がネズミの胃にゴキブリを中間宿主とする特殊な寄生虫で癌を発生させたということで、1926年にノーベル賞を受賞しました。今日、癌に関する欧米の教科書にはフィビガー教授の名前は出てきませんが、Yamagiwa and Ichikawaのタール癌は必ず記載されています。二人はこの仕事で1919年に学士院賞を受賞しました。市川厚一、31歳。後に北大獣医学部に戻り、比較病理学講座を創設しました。今でも研究院長室には市川博士の「努力」「忍耐」の書が飾られています。また、市川博士がつくったウサギの耳のタール癌は北大博物館と獣医学研究科標本室に展示されています。
喜田宏先生とインフルエンザ

毎年、冬にインフルエンザが流行します。インフルエンザウイルスは、年々、抗原変異を起こします。そのため、ワクチン製造用のウイルス株を毎年替えます。次にどのようなウイルスが流行するかを予測して、インフルエンザシーズンが始まる前にワクチンを造っておく、これが真の予防です。それができないのは、抗原変異がどのような機序で起こるのか、解っていなかったためです。
喜田先生は、獣医学研究科修士課程を修了後、製薬会社でインフルエンザワクチンの開発・改良研究と製造の指揮をとられました。その中で、抗原変異とは何か、パンデミック(世界流行)ウイルスはどのように出現するのかを解明するために、昭和51年に本獣医学研究科に戻られ、以来研究を続けられました。抗原変異は、ウイルス集団内に既に存在する変異ウイルスがヒトの免疫圧下で選択される結果であることが分かりました。インフルエンザが人獣共通感染症であることを確定し、動物とヒトのインフルエンザウイルス遺伝子の起源が渡りガモの腸内ウイルスにあり、北方圏のカモの営巣湖沼がウイルスの貯蔵庫であることをつきとめました。また、パンデミックウイルスは、ブタの呼吸器にヒトのウイルスとカモ由来のウイルスが同時感染して生ずる遺伝子再集合体であることを実証しました。さらに、抗体がウイルスの感染性を中和する新たな分子機構を見出しました。これらの研究成果に基づき、動物とヒトのインフルエンザをコントロールする方策を提唱するとともに、人獣共通感染症の克服に向けた国家プロジェクトを提案・推進されました。このプロジェクトの使命を果たすために、本学に世界で初めて人獣共通感染症リサーチセンターを創設されました。喜田先生の業績は、獣医学、ウイルス学等への学術的貢献が顕著であるのみならず、家畜衛生、公衆衛生、さらには予防医学等の応用分野の進歩に寄与するところが多大で、国際的にも人獣共通感染症の疫学研究モデルを提示したものとして、極めて高く評価されています。
喜田先生は、熟慮の上で提言、自ら実行、ゴールに向けて努力する姿勢を堅持し、直球をど真ん中に投げ続ける。そんな人柄でぶれないため、頑固親父に見えますが、正面から飛び込んでくる人は、誰でも何時でも寛容に受け入れる優しい心をお持ちです。したがって、教え子や多くの研究者の心を鷲掴みにします。これまで数々の専門家を育成して、国内外に輩出された事実が、喜田先生の研究に対する熱意と愛情の籠もった指導力の証左です。今もなお、北海道大学ユニバーシティプロフェッサーとして、元気にご活躍中です。
北大獣医学部とアフリカ・ザンビア大学獣医学部の連携

北海道大学獣医学部とザンビア大学との連携の歴史は30余年を数え、本邦の大学とアフリカの大学の発展的な関係としては代表的なものとなっている。この連携は、ザンビア共和国からの要請で当地に獣医学教育を根付かせるという壮大なプロジェクトに本学部が中心となって関わったことからはじまった。当時のザンビア共和国では、他の旧英国領の国々と同様に現地の人々がそれぞれの国内で獣医師養成教育を受ける機会は与えられていなかった。独立後約20年が経過したザンビア共和国国内には獣医師が10数名しかおらず、獣医学的管理がない国では家畜の病気が蔓延し、その生産性の低下、そして食の安全性が確保されず、鉱物資源に代わる外貨獲得手段となりうる農畜産物の輸出などできる状況ではなかった。
日本政府の無償資金協力によってザンビア大学に建設された獣医学部の建物が落成する2年前から、国際協力事業団(JICA)(当時)の技術協力プロジェクトとして派遣された本学獣医学部の教員・卒業生を中心とした日本人教員が主役となり、英国、ベルギー、オランダ、オーストラリアなどの援助機関を通して派遣された教員、そしてザンビア大学がインド、ナイジェリアから雇用した教員も加わって、同国、アフリカ南部の新興独立国の自国内で初めて行われる獣医学教育が開始された。1990年には同国で教育された初めての獣医師が卒業した。初期の卒業生の中から優秀で向学心・向上心が旺盛で優秀な学生を文部科学省の国費留学生として本学をはじめ国内の獣医学系大学院に留学させて博士号を授与し、それら卒業生の多くはザンビア大学に教員として教育の独力化に尽力した。
JICAによる初期の技術協力が終了した後も、本学部の教員は積極的な関係を模索し、個々の科学研究費補助金などで帰国した学生への支援を継続し、JICAによるザンビア大学獣医学部を利用した獣医学教育普及の新プロジェクト、本学部による文部科学省補助事業(Good Practice)による学生交流プログラム、本学部とかかわりの深い人獣共通感染症リサーチセンターのザンビア研究拠点、ザンビアを基盤としたアフリカ大陸における環境毒性に関する研究コンソーシアム形成、感染症や環境汚染対策などの社会実装型大型研究プロジェクトなど、本学部主体の支援からはじまったザンビア大学獣医学部との関係は、やがて双方向の強い連携へと発展してきた。
現在、2つの北大側主導大型研究プロジェクト、世界銀行から支援を受けたザンビア大学主導の大型研究プロジェクト研究などが推進され、また、大学間の関係の深まりによって本学がザンビア大学に設置した在外事務所において、優秀なサブサハラ・アフリカの学生を日本の大学へ誘導するための拠点として活用されるなど、本学部とザンビア大学の連携はその深化を進めている。