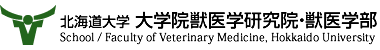令和6年度 獣医学部同窓会通常総会・
第13回北海道大学獣医学部同窓会フォーラム報告
1.通常総会報告
令和6年度獣医学部同窓会通常総会は、午後1時より、獣医学部講堂で44名の出席者(オンライン出席3名を含む)のもと、開催されました。議長に、昆泰寛氏(昭56卒)が選出され、副議長に中村健介氏(平17卒)、議事録署名人に磯田典和氏(平17卒)が指名され、議案が審議されました。中には、今後の同窓会の運営に関わる重要議案も含まれており、多くの意見が飛び交う活発な総会となりました。多くの建設的なご意見をいただいた会員の皆様に感謝いたします。
中でも、議案第4号「令和6および7年度からの会報発行形態について 2)令和7年度会報からの会報発行形態について」、および 議案第6号「会則の一部変更について」は、重要な議案であり、審議の結果、以下の通り認められました。
議案第4号 令和6および7年度からの会報発行形態について
2)令和7年度会報からの会報発行形態について
令和6年度総会、会報、Websiteで周知のうえ、
| 1) | 同窓会の財務逼迫を緩和するため、R6年度から会報をスリム化し、一部の内容を会報から外しwebsiteで閲覧できるようにする。 |
| 2) | 同窓会の財務が逼迫しており、昨年と同様の会費納入状況では、R7年度は同窓会報と名簿一体となった会報を発行できない可能性があるため、同窓会会員には会費の納入を切にお願いする。来年3月までの同窓会費の納入状況を見て最終判断をする。財政的に難しい場合は、R7年度は同窓会報から名簿を切り離して同窓会報のみの発行となる可能性があることを第67号で周知する。R8年以降の同窓会報の発行形態(同窓会報と名簿の合併号あるいは同窓会報のみ)はR7年度の財務状況を見て判断する。 |
| 3) | R7年度から長期間会費未納者への国内外への会報発送を中止する。ただし、会報はwebsiteで閲覧できるようにする。 |
| 4) | 令和5年度には中止した、過年度会費未払い分について、以前に実施していたように5年分の未払い分の納入を依頼する。 |
以上1〜4)により財政の安定化を図る。さらに、
| 5) | マイページの有効活用、メールアドレスの登録推進の周知を継続するとともに、会費収入の向上に努める。 |
| 6) | 仮に、名簿が発行されない場合でも申請により名簿を印刷物として発送する。 |
| 7) | Websiteでの情報発信を充実させる。 |
| 8) | 同窓会報をより魅力的なものとするため工夫する。 |
| 9) | 同窓会事務局がマイページを管理しやすいよう変更を加える。 |
| 10) | マイページによる名簿管理を推進するとともに、合併号が発行されない年であっても、名簿の質・精度向上に努める。 |
| 11) | 上記を推進するため、実質的な同窓会事務局の設置に必要な財源確保、ならびにその設置を模索する。 |
以上により、持続可能な同窓会の運営を担保するとともに、同窓生への情報発信、並びにサービス向上を図り、より密接な同窓生の連携による社会的価値の創出と同窓会のさらなる発展のため、さらには、より一層、同窓生から母校への支援が得られるよう、本会の運営に努める。
議案第6号 会則の一部変更について
これまでは、会則第29条に規定されるとおり、入会後50年を経た正会員の年会費を免除しておりましたが、これを、会員歴50年を経た後も、引き続き会費を納入していただくことを妨げない旨に変更。

2.第13回北海道大学獣医学部同窓会フォーラム報告
令和6年9月28日、同窓会総会に引き続き、「国際共修、多文化間共修環境の先進部局として」と題して13回北海道大学獣医学部同窓会フォーラムを開催しました。
COVID-19のパンデミックで一時中断されていた学生の海外活動が再開されたこと、過去5年以上これに関連するテーマで同窓会フォーラムが開催されていなかったこと、また、同窓会員をはじめ多くの方からご寄付いただいた「学術交流基金」から海外渡航時の保険料の支援してきたことなどから、獣医学部および研究院が実施している活発な国際活動の一端を同窓一同が共有することを目的として、担当教員等からのプログラムの説明に続き、実際に活動を経験した学生から体験談を話していただきました。学部の取り組みでは、タイ、イギリス、ザンビアでの活動内容、大学院の取り組みでは、卓越大学院プログラムに関連した内容を紹介いただきました。改めて、獣医学部および研究院が「国際共修、多文化間共修」を活発に推進していることを実感しました。
当日は会場で44名、オンラインで3名の参加があり、獣医学部および研究院の特色ある活動の一つとして、このような国際的活動を継続することの重要性を再認識した次第です。
趣旨説明
大学の国際化、グローバル人材の育成など、大学が目指す方向性の一つとして重要視されています。大学には海外大学との学術交流協定の締結と交流事業の実質化、国際共同研究の推進、留学生の受け入れ、あるいは、学生の海外派遣など様々な取り組みが求められています。このような国際活動の継続は、我が国の大学の国際競争力の強化、ひいては、日本の国際競争力の強化に繋がると期待されています。一方で、大学における実質的な国際活動は、一朝一夕に推進できるものではなく、当該部局や教職員の信念と熱意による継続的な取り組み、信頼できる海外カウンターパートの存在、なによりも、互尊の精神を土台として双方がその有益性を享受できる環境の構築が必要です。
北海道大学は「国際性の涵養」を教育理念の一つに掲げています。中でも獣医学部は、ザンビア大学獣医学部設置への協力以降、半世紀におよぶザンビアとの連携、エジンバラ大学との学生相互派遣を伴う交流、大学の世界展開力に端を発するタイ獣医系大学との単位認定を伴う学部学生の相互派遣、JICA技術協力プロジェクト、あるいは地球規模課題対応国際科学技術協力プログラムの実施など、多くの国際活動を実施しています。大学院教育でも、教育の完全英語化、海外インターンシップの導入、その他学生の国際活動の支援など、北大のグッドプラクティスとなる多くの国際的な活動を実施しています。
昨今、大学のグローバル化の方向性を示す言葉として「国際共修」、「多文化間共修」を耳にする機会が多くなっています。留学生と日本人学生が共に共通課題に取り組む「多文化間共修」、文化や言語の異なる学生が、グループワークやプロジェクト等での協働学習体験を通して、実質的な交流により相互理解を深める「国際共修」、ともに、獣医学部、および、獣医学院・国際感染症学院では、新しいものではなく、当たり前のように実践しています。同窓兄姉から受け継がれてきた「国際感覚の涵養」、「国際社会への貢献」、「グローバルに活躍できる人材の育成」などの意識が、学部・大学院の潜在意識としてインプリントされており、社会の趨勢に流されることなく、地に足の着いた国際活動を継続しており、北大の国際共修、多文化間共修環境の先進部局として、ロールモデルとなる取り組みを進めています。
フォーラムでは、国際的な活動のグッドプラクティスとして、学部学生の海外派遣を伴う「国際獣医師人材を育成する獣医学教育世界展開プログラム(IVEP)」、および、北大全体の大学院教育改革のロールモデルとなる卓越大学院プログラム「One Healthフロンティア卓越大学院プログラム」における「国際共修、多文化間共修環境」の実例を、その活動を経験した学生が紹介して同窓兄姉と共有いたします。今後の「国際共修、多文化間共修」の推進について、高所からご指導ご鞭撻いただく機会となれば幸いです。
|
タイ・チュラロンコン大学/カセサート大学派遣・受入 タイ・チュラロンコン大学/カセサート大学との学生交流 獣医学研究院・教授 野中 成晃(昭和60年卒) チュラロンコン大学の生徒から得たもの 学部5年 阿部 栞里 タイ・カセサート大学への派遣を終えて 獣医学研究院・助教 前園 佳祐 (令和3年卒) |
 |
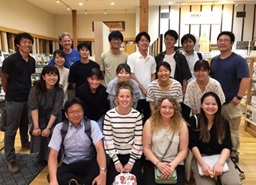 |
英国・エジンバラ大学派遣・受入 学部における国際共修:英国エジンバラ大学派遣と受入 獣医学研究院・教授 坪田 敏男(昭和58年卒) 2023エジンバラ大学派遣報告 学部6年 井上 祐人 |
|
ザンビア・ザンビア大学派遣 北大獣医学部とザンビア大学獣医学部との連携 獣医学研究院・准教授 村田 史郎(平成16年卒) ザンビア大学派遣報告 学部5年 後藤 美空 |
 |
 |
大学院における国際共修、多文化共修 国際共修、多文化共修を実践する大学院教育 獣医学研究院・教授 堀内 基広(昭和61年卒) 多様性の尊重から生まれる創造性 国際感染症学院D3 川口 虹穂 大学院プログラムにおける海外活動 国際感染症学院D4 有泉 拓馬 (令和3年卒) |