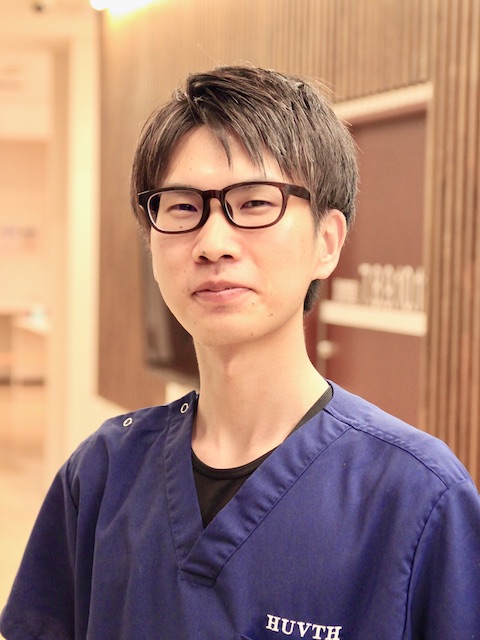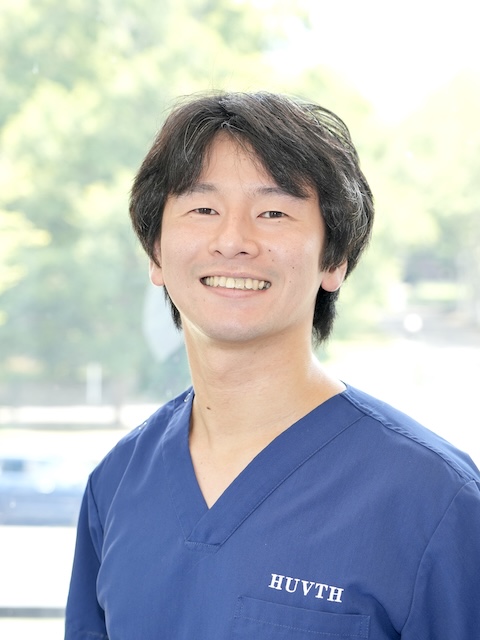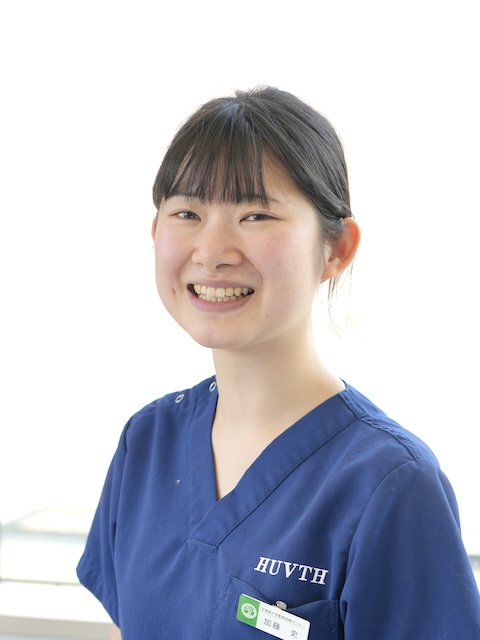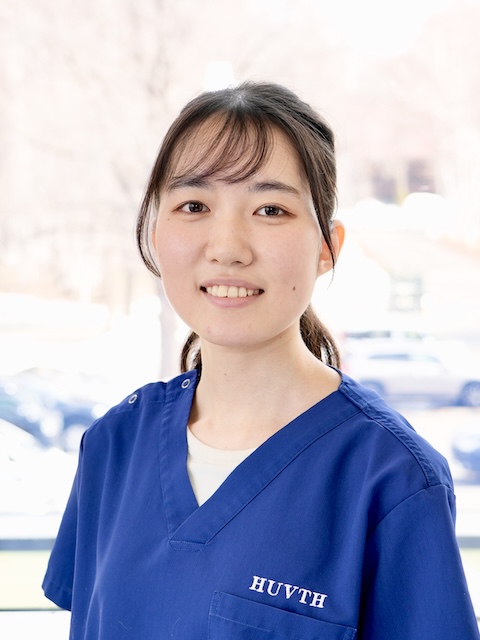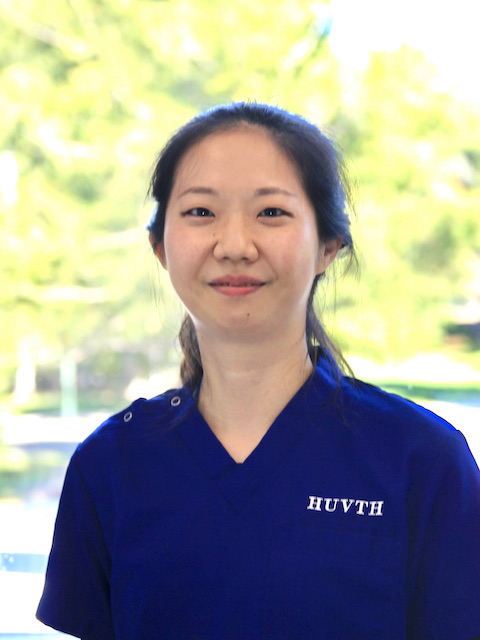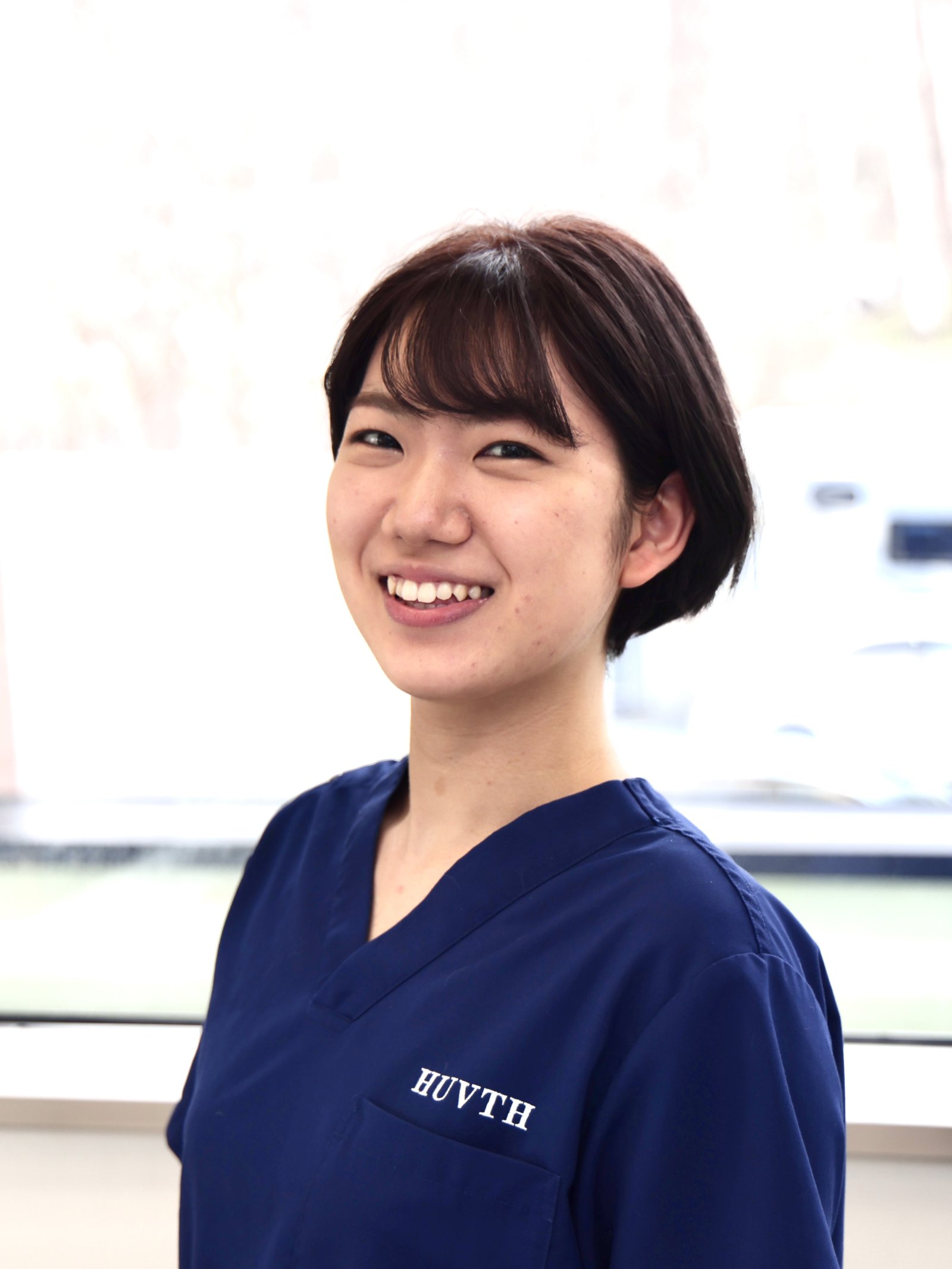体の中では様々なホルモンが分泌されており、ひとつひとつのホルモンがとても大切な役割を担っています。ホルモンの分泌によって体の機能を調節する仕組みを「内分泌」と呼び、ホルモンのバランスが崩れることによって起こるのが「内分泌疾患」です。
ホルモンの作用は多岐に渡るため、内分泌疾患の動物は様々な症状を示します。特徴的な症状を示さないことも多いため、「年のせいだろう」と思っていた症状の原因が実は内分泌疾患だった、ということもよくあります。ホルモンの仕組みはとても複雑なため、単にホルモンを測定するだけでは内分泌疾患を診断することはできません。ホルモン検査の結果だけでなく、症状や画像検査と合わせて総合的に診断することが重要です。
内分泌内科では、多様な症状を示す内分泌疾患を的確に診断し、その子に合った最適な治療をご提案させていただきます。コントロールがむずかしい難治性の内分泌疾患の内科治療も担当いたします。
内分泌疾患の画像検査
症状やホルモン検査だけでは診断がはっきりしない場合、画像検査が診断の決め手になることがあります。超音波検査、CT検査、MRI検査などの高度画像診断装置を駆使し、ホルモンを産生する臓器の異常を検出します。
高カルシウム血症の犬の甲状腺と上皮小体の超音波検査画像。甲状腺(破線)領域に、5 mm大に腫大した低エコー源性(黒い)の上皮小体腫瘍(矢頭)が見つかりました。超音波検査は、数mmの小さな腫瘍でも明瞭に検出できます。

副腎皮質機能亢進症(クッシング症候群)が疑われた犬の副腎の超音波検査画像と頭部MRI検査画像。副腎は正常な形態を保ったまま腫大し(左の画像)、下垂体には腫瘍(右の画像の破線)が見つかりました。症状およびホルモン検査の結果と合わせて、下垂体腫瘍によるクッシング症候群と確定診断しました。

特殊な内分泌検査
上記とは逆に、画像検査からは内分泌疾患が疑われるものの、症状がはっきりしない場合もよくあります。特に最近では、健康診断で超音波検査を行った際に副腎の腫大が偶然見つかる機会が増えています。そのような場合、一つのホルモンを測定するだけでは診断できないことが多くあります。血液中と尿中の複数のホルモンを一斉に測定することで、ホルモン異常を詳細に評価でき、適切な診断が可能となります。検査の詳細については、担当医までお問い合わせください。